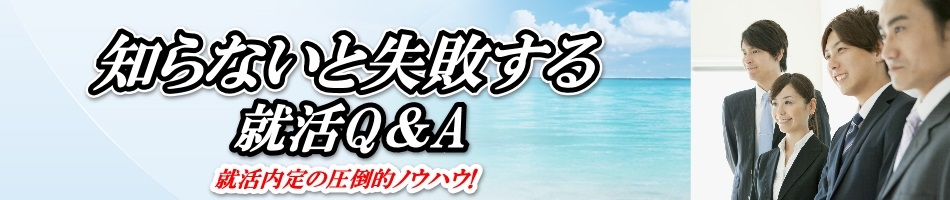【グループディスカッションのSTEP⑫】~ケーススタディ~
前回は、就活のグループディスカッションの、
インバスケットの進め方について解説させて頂きました
今回は、グループディスカッションのディベートの進め方について、
お話させて頂きます
「売り上げを2倍にするための施策を考えよ」などのテーマで話し合うケーススタディは、
基本的にに選考の終盤で実施されます
他の3つで重要なのはコミュニケーション力でしたが、
ケーススタディは、地頭力や問題解決力が重視されます。
ですので、事前に対策しないと通過するのは難しいかもしれません
問題解決にはプロセスがありますので、
それを事前に知っているだけで、差がついてしまいます
「日本全国のコンビニの数を考えよ」などのフェルミ推定は、
外資やコンサルで出題されるのが一般的なので、
この2つを志望していないなら対策を問題解決に絞るのがいいですね
問題解決の対策本は、東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるや世界一やさしい問題解決の授業
などがオススメですね
ケーススタディの基本的な流れとしては
①役割を決める
②時間配分を決める
③定義・目的を共有する(前提を揃える)
④問題・課題を明確にして、解決策を考案する
例えば、売り上げUPするというテーマであれば、
まず客単UP、客数UPの2つの切り口が考えられます
そのどちらかに、問題・課題を抱えていないか?を考えます
それを明確にした上で、施策を考えていきます。
例えば、こんな感じです
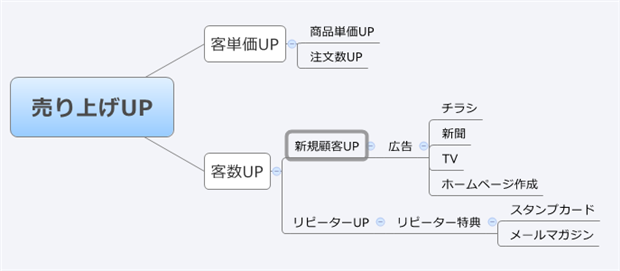
⑤限られた条件の中から、優先順位をつける
施策によっては、結果が出るまで時間を要すものもあるでしょう。
そういった場合、時間配分にもよりますが、
事前にどちらかに条件を絞ることも大切になてくるでしょう。
短期スパンだとでは、即効性の施策に絞ればいいですし、
中長期スパンでは、遅効性の施策で考えればいいです
繰り返しになりますが、ケーススタディは、やはり、事前の対策が重要です
ですので、事前にグループディスカッションが選考終盤に、
実施されると分かっているのであれば、対策をするようにしてください
この記事と関連する記事
- 【グループディスカッションのSTEP①】~目的~
- 【グループディスカッションのSTEP②】~流れ その1~
- 【グループディスカッションのSTEP③】~流れ その2~
- 【グループディスカッションのSTEP④】~評価基準 その1~
- 【グループディスカッションのSTEP⑤】~評価基準 その2~
- 【グループディスカッションのSTEP⑥】~評価基準 その3~
- 【グループディスカッションのSTEP⑦】~評価基準 その4~
- 【グループディスカッションのSTEP⑧】~種類~
- 【グループディスカッションのSTEP⑨】~自由討論~
- 【グループディスカッションのSTEP⑩】~ディベート~
- 【グループディスカッションのSTEP⑪】~インバスケット~